呼吸器疾患
気管支喘息
気管支喘息は、「気道の慢性炎症を本態とし、臨床症状として変動性を持った喘鳴、呼吸困難などの気道狭窄や咳で特徴付けられる疾患」とされており、変動性疾患であると考えられています。つまり、喘息の人の気道は、症状がないときでも常に炎症をおこしていて、とても敏感になっていてるのです。ですから、正常な気道ならなんともない風邪や天候、ほこり、疲労、ストレス、花粉、タバコ、運動などの様々な要因によって、発作がおきてしまうのです。
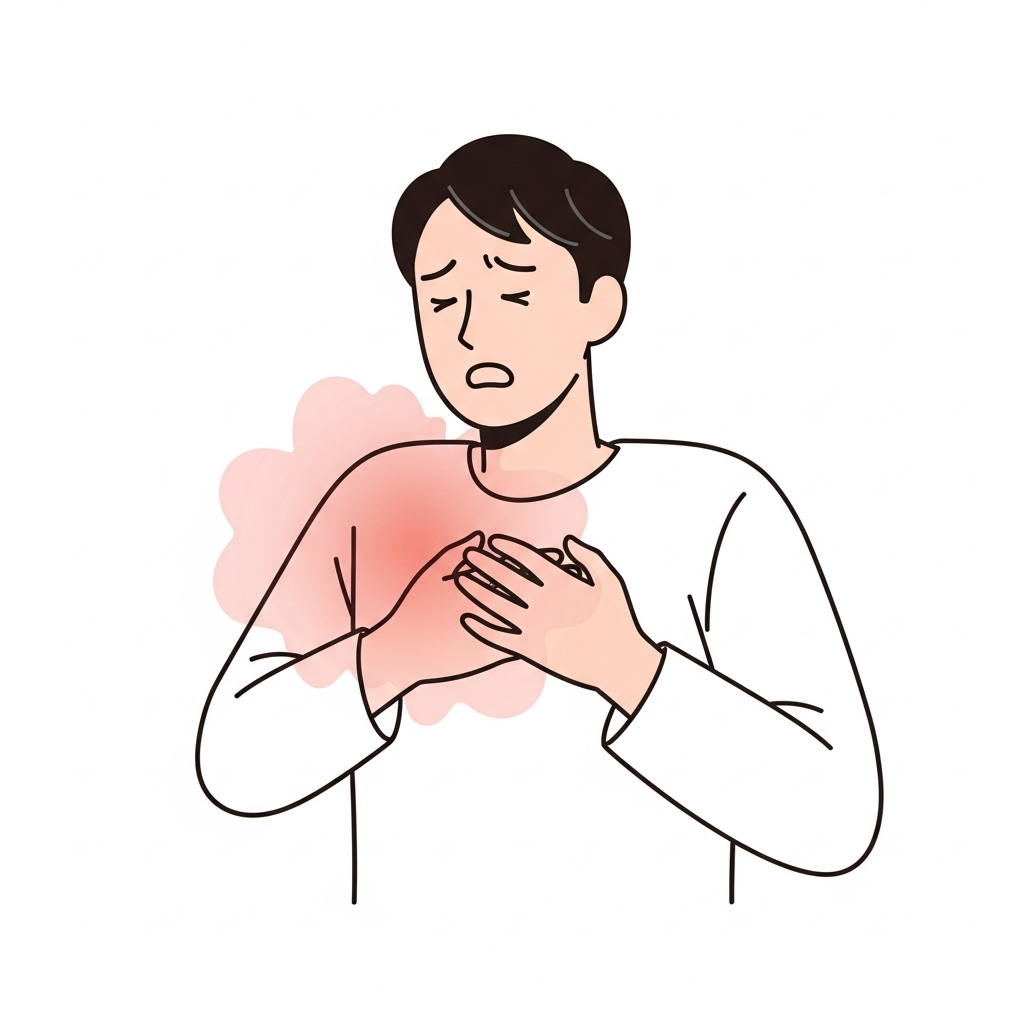
気管支喘息の診断方法
- 発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳(夜間、早朝に出現しやすい)の反復
- 可逆性の気流制限
- 気道過敏性の亢進
- アトピー素因の存在
- 気道炎症の存在
- 他疾患の除外
- 5は通常、好酸球性である
- 上記の1、2、3、6が重要である
- 4、5の存在は症状とともに喘息の診断を支持する
1は詳細な問診・聴診で分かります。
2、3は気管支収縮薬や気管支拡張薬を吸入して呼吸機能検査を必要に応じて行います。
4は問診でも分かりますが、血液検査でも判断可能です。
5に関しては、呼吸機能検査・聴診・詳細な問診等で総合的に判断致します。
6は非常に大切で、当クリニックでは胸部レントゲン撮影もしくは胸部CT撮影を行うようにしています。
気管支喘息の治療
ぜんそくの治療で重要なのは、発作のベースとなる慢性の気道炎症を鎮めることです。
ぜんそくの薬物療法は、「気道の炎症をおさえる薬(抗炎症薬)」と「せまくなった気道をひろげて発作をおさえる薬(気管支拡張薬)」の大きく2つに分けられ、特に抗炎症薬が発作の予防薬として主役を演じます。
抗炎症薬の代表、吸入ステロイド薬
吸入ステロイド薬(副腎皮質ホルモン薬)は、最も強力な抗炎症作用を持ち、気道の過敏さをよく改善し、ぜんそく治療の基本薬といえます。
飲み薬や注射のステロイド薬では、長期間使い続けると「胃かいよう」「糖尿病」「骨粗しょう症(骨がもろくなる)」などの副作用が問題となります。一方、吸入ステロイド薬は、粉末または霧状のものを直接吸い込み気道に届かせることで、ごくわずかな薬の量で気管支に直接作用させることができるので、全身の副作用の心配がなく安心して使えます。
最近になり、小児に対しても世界的に第1選択薬として推奨されるようになりました。抗アレルギー薬も抗炎症薬に分類されますが、吸入ステロイド薬に比べ効果は弱いです。テオフィリン薬にも弱い抗炎症作用があります。
症状を緩和する気管支拡張薬
気管支拡張薬は、長時間作用が持続して日常の症状を抑えるものと、即効性で短時間作用して発作のときに緊急に用いるものと、大きく2つに分けられます。
前者には、徐放性テオフィリン薬(内服)、長時間作用性β刺激薬(吸入、貼り薬、内服)があります。
後者の「発作止め」の代表は、短時間作用性β刺激薬の吸入薬です。スプレー状の薬を吸入することで発作を鎮められますが、抗炎症薬を使わずにこればかりに頼っていると、重度の発作に移行して手遅れとなりうるので注意しましょう。
アスピリン喘息
アスピリン喘息(AIA : aspirin induced asthma)とは、アスピリンおよびアスピリンと同様な作用がある解熱鎮痛剤(解熱剤、鎮痛剤、風邪薬、坐薬、湿布など)などによって誘発される喘息のことです。しかし、最近では、アスピリンだけに対する過敏症と混同されやすいため、NSAIDs過敏喘息と呼ぶ方が良いともされています。
成人喘息患者さんの約5~10%にみられ、解熱鎮痛剤だけでなく、食品や薬剤に含まれる色素、防腐剤などによって誘発されることがありますので注意が必要です。

アスピリン喘息を誘発する物質
酸性抗炎症薬(非ステロイド性解熱鎮痛剤)
(NSAIDs: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)
アスピリンの注射薬は1992年までは使用されていて、発熱などの症状に優れた効果がありました。しかし副作用で死亡した例があったため使用中止となり、現在は発売されていません。
内服薬や外用薬でよく使用されるものに、アスピリン(市販薬バファリンなど)、インドメタシン(インテバンなど)、エテンザミド(市販薬セデス、ノーシン、ナロンエースなど)、ケトプロフェン(モーラスなど)、ジクロフェナック(ボルタレンなど)、ナプロキセン(ナイキサン)、ピロキシカム(フェルデンなど)、フェルビナク(セルタッチなど)、ブルフェン(市販薬ルル、イブ、ベンザブロックなど)、メフェナム酸(ポンタール)、ロキソプロフェン(ロキソニンなど)など多くの薬剤があります。
一般に市販されている大部分の総合感冒薬には、解熱鎮痛薬が使用されており、アスピリン喘息の方は市販されている総合感冒薬や鎮痛薬は使用を避けるべきです。
医薬品添加物
喘息発作の点滴治療に使用されるステロイド薬のうち、ソルメドロールやソルコーテフなどコハク酸エステル型のステロイドは、アスピリン喘息の患者さんには使用できません。
食品、食品添加物
タートラジン(食用黄色4号)、安息香酸ナトリウム(防腐剤)、ベンジルアルコール(香料)などが食品に含まれていて発作を誘発します。また果物などに含まれるサリチル酸化合物でも過敏反応が起こることがあります。
その他インスタント食品で内容が不明なもの、人工着色料、香料を含んだケーキ、お菓子などは避けた方がいいでしょう。成分表示に注意し、食べた時におかしいと思った食品は覚えておきましょう。
アスピリン喘息の診断
アスピリン喘息は、思春期以降、20~40歳代(平均30歳代)に発症することが多く、小児ではまれです。一般的に、解熱鎮痛剤を服用してから15~30分後に喘息発作が起こります。
また、アレルギーのはっきりしない患者さんに多くみられ、発作に季節性はなく、一年中みられます。喘息症状が重症、難治性で、死亡例が通常の喘息患者さんよりも多くみられます。70%以上の患者さんが慢性副鼻腔炎(蓄膿症)や鼻茸(鼻のポリープ)を合併しており、早期から臭覚低下を伴っている場合が多いのも特徴です。
アスピリン喘息の治療
長期管理は通常の気管支喘息と同様で吸入ステロイド薬が基本となります。また、ロイコトリエンの過剰産生があるため、ロイコトリエン受容体拮抗薬も有効です。
また、基本的にはすべての解熱鎮痛薬(酸性)を徹底してさけること、さらに食品・医薬品の添加物を除外することが治療となります。
アスピリン喘息の患者さんが熱や痛みのある時
酸性抗炎症薬は使用できませんが、ソランタール、モービック、セレコックスなどの塩基性抗炎症薬は発作を誘発しませんので使用できます。また、カロナール、コカールなどのアセトアミノフェンも安全だと言われています。かぜ薬ではPL顆粒、ピーエイ配合錠が使用できます。但し、これらの薬でさえ、添付文書の禁忌に「アスピリン喘息」の記載があります。
最後に
アスピリン喘息を誘発する物質は薬剤にとどまらず、食品など多種類に及ぶため薬剤だけに注意していても、発作がなかなか治まらないことがあります。重症の場合生命にかかわりますので、毎日の生活で注意が必要です。
また医療機関を受診する際には、アスピリン喘息であることをはっきりと告げることが大切です。
せき喘息
- 鼻水、発熱、咽頭痛などの風邪症状は治ったのに、咳だけが続く。
- 市販の風邪薬や咳止めを飲んでいるのに、一向に咳が止まらない。
- 夜間から明け方にかけて咳き込みが激しくて眠れない。
こんな症状で困られていませんか?上記のような咳が続く方は「せき喘息」かも知れません。「せき喘息」はあまり知られていない病気ですが、近年確実に増加している病気です。
わが国の慢性の咳の30%以上がこのせき喘息によると報告されています。喘鳴(ゼイゼイ・ヒューヒュー)や呼吸困難発作が無いことで喘息とは区別されますが、簡単に言えば、喘息の前段階あるいは軽症型として位置づけることができます。実際、喘鳴を起こす典型的な喘息と比べても、気道の炎症の程度、気道過敏性などの病態を示す様々な指標が軽症の喘息といえる範囲にあり、アレルギーの関与の程度も同程度です。
せき喘息の患者さんは、喘鳴がないために自分が喘息であるとは思いもよらず、咳止めだけを処方されて飲み続けるが効果がないといったことをよく経験します。せき喘息の咳には通常の咳止めは効かず、β2刺激薬が有効であり、このことが診断をつける上で重要とされています。

せき喘息の診断方法
せき喘息の診断には、問診が非常に大切です。咳が出るようになったきっかけや時期、咳や痰の状態、起こりやすい時間帯などは当たり前のことですが、アレルギーに関する既往歴や家族歴も重要な診断材料です。
一応、せき喘息の診断基準は以下の7項目になります。
- 喘鳴を伴わない咳が8週間以上続く
- 喘鳴や呼吸困難などを伴う喘息にかかったことがない
- 8週間以内に上気道炎(風邪など)にかかっていない
- 気道が過敏になっている
- 気管支拡張剤が有効な場合
- 咳を引き起こすアレルギー物質などに反応して咳が出る
- 胸部レントゲンで異常が見つからない
「一応」と書かして頂いたのは、1や3のように8週間も咳を放置しておく患者さまはいらっしゃらないからです。早い方では1週間の咳で来院される方もおられます。また、2に関しては、小児喘息にかかっていたが完治した成人の方も沢山いらっしゃるからです。さらに,4や6も即座に調べようがありません。
ですから、せき喘息の診断は非常に難しいのです。当クリニックでは、聴診で肺雑音が聞き取れなくても、7の胸部レントゲンは確認するようにしています。また、5の確認のために、最初の投薬は7日分程度としています。結局は、問診が非常に重要な診断材料となるのです。
せき喘息の治療
市販薬や処方薬のかぜ薬や抗生物質、咳止めなどを用いても、せき喘息の場合はほとんど効果がありません。基本的には、症状の所で書いた①気道が狭まって、②刺激に過敏になって、③炎症を起こしている状態を改善する治療が必要です。
従って、①に対しては気管支拡張薬、②に対してはロイコトリエン受容体拮抗薬(抗アレルギー薬)、③に対しては吸入ステロイド薬を使います。吸入ステロイド薬は、少量でも気道に直接作用して、優れた抗炎症作用を発揮します。全身的な副作用も非常に少なく、安心して長期間使用することが出来ます。
治療を開始して1~2週間で咳は劇的に改善するはずです。(改善しない場合は、他の原因を考える必要があります。)症状が良くなったからといって、治療を中断すると再発することがあるので、数ヶ月間は根気よく治療を続ける必要があります。ただし、その間に症状の改善と共に、薬の種類や量は減らしていき、最低必要量を見つけることが大切です。
せき喘息の患者さまの約30%が気管支喘息に移行するといわれています。気管支喘息への移行を食い止めるためにもできるだけ早い段階で薬を使って、気道の炎症を抑える必要があります。特に吸入ステロイド薬の使用は「咳症状の治療」とともに「喘息への移行を予防する」効果が期待できます。
妊娠と気管支喘息
妊娠中や授乳中の喘息治療については、「薬を使っても大丈夫なの?」と不安に思われる方も多いかもしれません。
実際、妊娠・出産は女性の身体に大きな変化をもたらすため、喘息との付き合い方にも注意が必要です。
詳しくは、「妊娠と喘息の関係について」のページでわかりやすく解説しています。
アトピー咳嗽(がいそう)
アトピー咳嗽は、慢性的に咳だけが続く気管の病気です。
あれ?咳喘息とどこが違うの?と思われた方もおられると思います。実は1文字だけ違っています。よく見てみてください。咳喘息は「気管支の病気」であり、アトピー咳嗽は「気管の病気」なのです。(わかりやすく言うと、)
原因も咳の症状も全く咳喘息と同じなのです。ですから、この2つの病気を初診時で鑑別することは、ほとんど不可能といえるでしょう。唯一、アトピー咳嗽と診断できるのは、初診時に処方させていただいた気管支拡張薬の効果がなかった場合です。
そして、抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗薬)または/および吸入ステロイド薬に効果があった場合です。
ということは、治療してみないと診断できないってこと?と思われるでしょう。悲しいかな、その通りなのです。こういう場合を、「治療的診断」といいます。(決して言い訳ではありません)
アトピー咳嗽の診断基準を記載しておきますが、診断基準自体がそういう考え方なのです。
- 喘鳴や呼吸困難を伴わない乾性咳嗽が8週間以上続く(咳喘息と全く同じ)
- 気管支拡張薬が無効である(治療してみないと分からない)
- アトピー素因を示唆する所見(注①)を1つ以上認める(咳喘息でもアトピー素因は多く認めます)
- 抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗薬)または/および吸入ステロイド薬にて咳嗽発作が消失する (治療してみないと分からない)
※注 アトピー素因を示唆する所見
- 喘息以外のアレルギー疾患の既往または合併
- 末梢血好酸球増加
- 非特異IgE値の上昇
- 特異的IgE陽性
ですから、当クリニックでは最初の投薬は1週間程度と決めています。そして、薬の効果を必ず確認していますので、ご安心ください。また、咳喘息と違って、アトピー咳嗽が気管支喘息に移行することはありませんが、しばしば再発を繰り返します。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
「慢性閉塞性肺疾患(COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease)」は、喫煙によって起こる肺の疾患です。(従来、「肺気腫」と「慢性気管支炎」と呼ばれていた疾患の総称です。)
国内の潜在患者数は500万人以上といわれ、2010年以降、日本人の死亡原因の第9位にのし上がり、年間16,000人の命を奪っているのがCOPDなのです。また、在宅酸素療法(HOT: Home Oxygen Therapy)の基礎疾患として約45%を占め、最も多い疾患です。たばこの煙を長期間吸い込むことにより、徐々に肺が壊れ気道が狭くなっていく病気です。大体、「1日で吸うたばこの本数×年数」(喫煙指数)が400の方は約20%、1200を超える方は約70%の方がCOPDになると言われています。ではCOPDになると、どのような症状が出るのでしょうか?
まず、初期症状として「咳と痰」です。風邪が長引いてなかなか治らないと感じたら、実はCOPDだったということがあります。次に「階段の昇り降りや坂道で息が切れる」といった症状が出始めます。それが徐々にひどくなって「普通に歩いても息が切れる」、「家族と一緒に歩いていてもついていけない」など、こうなるとかなり進行しているサインです。その後は酸素を吸わないと動けなくなり、ちょっとしたことでも息ができなくなり、入退院を繰り返すことになります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断と治療
診断
COPDの診断には、スパイロメーターという機械を使った呼吸機能検査(スパイロメトリー)によって行います。この検査は、COPDの診断には欠かせない検査で、肺活量と、息を吐くときの空気の通りやすさを調べます。COPDの患者さまは、息が吐き出しにくくなっているため、1秒量(FEV1)を努力肺活量(FVC)で割った1秒率(FEV1%)の値が70%未満のとき、COPDと診断します。
また、胸部レントゲン写真で肺の部分の透過性亢進(黒っぽくなる)、横隔膜の平坦化を認めたり、胸部CTでは肺胞が破壊された肺気腫の部分が黒っぽく(低吸収域)写ります。また、COPDの診断だけでなく、「間質性肺炎」や「気管支拡張症」などの可能性を除外したり、「肺がん」の有無を確かめるのにも有用です。
診断
まず第一歩、大前提は禁煙です。禁煙無くしてCOPDの治療は成立しないといっても過言ではありません。その上で薬物療法が考慮されます。
COPDの長期管理において、長時間作用型吸入抗コリン薬、長時間作用型吸入β2刺激薬、貼付β刺激薬、吸入ステロイドという薬が治療の主役となります。これらを単独、あるいは併用して治療を組み立て、適宜、短時間作用型吸入β2刺激薬、あるいは短時間作用型吸入抗コリン薬を用い、さらに増悪を繰り返す場合には、吸入ステロイド薬を追加することになります。そして、薬物療法のみではどうしても難しい場合は、在宅酸素療法の導入となります。
スパイロメーター
「肺年齢」を知ることができる機器です。 「肺年齢」とは一秒間に吐ける息の量(一秒量) から、標準の方に比べて自分の呼吸機能がどの程度であるかを確認して頂くための目安です。
また、タバコをよく吸う人は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の発見やリスクを調べることができるため、定期的に検査されることをおすすめいたします。
「肺年齢」を知ることで肺の健康意識を高め、健康維持や呼吸器疾患の早期発見・治療に役立てることができます。

長引く咳(せき)
長引く咳にはさまざまな原因があります。
当院でよく見られる主な病気を、順にご説明します。
後鼻漏
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎があると、鼻汁が喉の後ろに垂れることによって長引く咳の原因になることがあります。小児ではゼーゼーなどの症状がみられることもあり、喘息といわれて治療をしているにもかかわらず、咳が良くならないときは、後鼻漏を疑う必要があります。抗生物質・抗ヒスタミン薬・去痰薬などを組み合わせて2週間くらい投与すると、症状は改善します。
副鼻腔気管支症候群(SBS:Sinobronchial syndrome)
SBSは、慢性的に咳が続く副鼻腔と気管支の病気です。これとせき喘息の違いは明らかですよね。副鼻腔がプラスされました。しかし、もう1点違うところがあります。お分かりでしょうか?実は、せき喘息は「咳だけが続く」ですが、SBSは「咳が続く」となっています。このちょっとした違いが非常に大切なのです。
SBSは、慢性副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)に慢性気管支炎などの気管支の炎症などが合併した状態で、原因は明らかではありませんが、鼻も気管支も一続きの気道なので、この気道の粘膜における防御機能が低下しているためと考えられています。ですから咳以外に、鼻閉や鼻汁(鼻水)、黄色っぽい痰が絡むなどの症状があることが、せき喘息やアトピー咳嗽とは異なります。
ただし…、せき喘息やアトピー咳嗽もアトピー素因に関係しているのですから、アレルギー性鼻炎を合併していても何もおかしくはありません。アレルギー性鼻炎でも鼻閉や鼻汁はありますし、後鼻漏(鼻汁が喉に垂れる)によって鼻汁を痰と思われる方もおられます。細心の注意を払って問診をしていますが、なかなか診断は難しいのが実情です。
当クリニックでは、上記の様にまずせき喘息の投薬を1週間行い、無効であればアトピー咳嗽とSBSの鑑別のために、鼻症状や痰の状態を再度確認し、SBSが疑わしい場合はレントゲン検査またはCT検査で慢性副鼻腔炎の有無を確認しています。
治療としては、マクロライド系抗生剤が第一選択となります。この抗生剤を4週間から8週間投与して、鼻症状と呼吸気症状の改善具合を診ていきますが、SBSに関しても、せき喘息やアトピー咳嗽と同様に「治療的診断」になることが多いのが現状です。
胃食道逆流症(GERD)
食道逆流症(GERD)の食道外症候群には、呼吸器疾患(症状)として、「明確な関連あり」の項目に咳嗽と喘息、が挙がっています。近年は慢性閉塞性肺疾患(COPD)への関与も報告されており、GERDの呼吸器への関わりは大きいです。中でも、8週間以上持続し胸部写真や身体所見の異常を示さない慢性咳嗽の原因として、GERDはかつてはわが国では稀とされたが近年増加しています。
GERDが咳を誘発し、また咳がGERDを誘発して悪循環を形成するため、咳喘息、副鼻腔気管支症候群など、慢性咳嗽のその他の原因疾患に高率に合併します。胸やけなどの食道症状や、起床時・食事中・就寝直後の咳の悪化、昼間優位の咳、咽喉頭症状の合併などの特徴的な病歴から疑い、薬剤による治療(プロトンポンプ阻害薬、消化管運動機能改善薬)や食事療法、肥満の回避などの生活指導を考慮します。他疾患合併例では、両者を強力に治療しないとしばしば軽快しないことがあります。慢性咳嗽の診療において、GERDは常に念頭に置く必要がある疾患です。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は本来、食道と胃の間の逆流弁(下部食道括約筋)の機能低下によって、胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。それによって、胸やけや、酸っぱい液体が上がってきてゲップが出る(呑酸:どんさん)、胸が締め付けられるような胸痛、喉の違和感や声枯れ(嗄声:させい)などの様々な消化器症状が出現します。
ところが、逆流した胃液が喉や気管を刺激したり、食道の粘膜を通して神経を刺激したりして、咳が出ることがあるのです。当然、逆流性食道炎自体が慢性的な病気ですから、咳も慢性的に出てしまいます。治療としては、通常の逆流性食道炎の治療と同じで、胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプインヒビター(PPI)が第一選択となります。胸やけ等の消化器症状は1週間ぐらいで改善する場合が殆どですが、咳の場合は長期の治療が必要なことが経験上多いようです。PPIが効けば、呼吸器系の薬は全く必要ないのです。つまり、この場合も「治療的診断」に該当すると思われます。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという微生物が感染しておこる病気です。しつこい咳と頑固な発熱が特徴ですが、肺炎という名前の割には、聴診器で呼吸音を聞いても異常がなく、外見だけではわかりにくい肺炎です。
また、家庭、学校、職場などの小集団内で流行するのも特徴で、かつては4年周期でオリンピック開催年に大きな流行を繰り返してきたため、「オリンピック病」と呼ばれていました。しかし最近は1984年と1988年に大きな流行があって以来、全国規模の大きな流行はみられていません。この数年は散発的な流行が多くみられ、2000年以降その発生数は毎年増加傾向にあります。
好発年齢は、幼児から成人まで幅広い年齢層でかかりますが、学童期、青年期によくみられます。潜伏期間は2~3週間と長いので、周囲にマイコプラズマにかかった人がいたら、しばらくは用心してください。
症状は、痰を伴わないしつこい咳と頑固な発熱が特徴で、全身倦怠感も見られますが、あまり重症になることはありません。また、普通の肺炎では、空気の通り道である気管支や肺胞が傷害されるため、ゼロゼロした痰が絡む音が聴診器で聴こえますが、マイコプラズは、気管支や肺胞の外部にある間質という組織で炎症を起こすため、ゼロゼロした音が聴こえないことが多く、診断が難しいのです。さらに、通常の肺炎では、白血球やCRP(炎症反応)が高値になりますが、マイコプラズマ肺炎では殆ど変化がなく、一般的な血液検査は当てになりません。
具体的には、症状が現れ始めた頃(急性期)と、2週間くらいしてすっかり回復した頃(回復期)の2回採血して、4倍以上抗体価が上昇していればマイコプラズマと診断できます。しかし、少々咳や熱があるからと言って、即座にマイコプラズマが疑われるわけではないので、病初期で採血されることはあまりなく、ある程度症状が進んでから検査されることが殆どです。この場合でも、回復期に2回目の採血を行えば、抗体の上昇が確認できることが多いのですが、治った後に受診する患者さまは殆どいませんので、結局2回目の採血が行われることも殆どありません。
当クリニックでは、マイコプラズマ抗原を調べる検査を行っています。この検査は、咽頭スワブ(ぬぐい液)で調べますので、採血の必要はなく、簡単に検査でき、結果もすぐわかります。
マイコプラズマに効く薬はマクロライド系の抗生物質ですが、最近このマクロライド系の抗生物質に効かないマイコプラズマ肺炎が増えてきました。マクロライド系の抗生物質が無効な場合には、テトラサイクリン系の抗生物質やニューキノロン系の抗菌薬が有効とされています。
百日咳
百日咳は、百日咳菌という細菌が感染しておこる病気です。苦しい特徴的な咳が長く続きますが、乳幼児では肺炎や脳症を併発して重症になることもあります。従来は、1才未満乳児に多く見られましたが、年長児や大人の百日咳も増えています。ワクチンの普及により、最近の統計では、1才未満乳児:13.6%、10~14才:15%、20才以上:38.2%と、むしろ年長児や大人の方が多く見られるようになってきました。
百日咳の咳は、大変特徴的です。気管支が痙攣するような咳です。まず、短い間隔で咳が連続的に出ます(エホ、エホ、コン、コンという咳)。続いて、急に息を吸い込んで、笛のような音が聞こえます(ヒューという呼吸音)。この笛のような音が、百日咳の咳の一番の特徴です。喘息発作では、息を吐く時にヒューという呼吸音が聞こえますが、百日咳では、息を吸い込む時にヒューという呼吸音が聴こえます。このような咳嗽発作を繰り返すことを「発作性痙攣性咳嗽」といいます。この咳嗽発作は、数分~30分も続くことがあります。しばしば、嘔吐を伴うこともあります。顔を真っ赤にして咳き込み、特に夜間に激しく咳き込みます。時として、呼吸が止まりそうになることもあります。
この「発作性痙攣性咳嗽」が、見られれば診断は簡単ですが、百日咳の患者さま全員に見られるわけではなく、症状だけから百日咳と診断することは難しいのが現状です。
一般的には、百日咳が産性する百日咳毒素(PT)に対する抗体(PT抗体)を調べて、抗体ができていれば百日咳と診断できます。採血してPT抗体が上昇していれば百日咳と診断できるわけですが、ちょっと問題があります。
ハッキリとした「発作性痙攣性咳嗽」があれば、百日咳を疑って採血しますが、年長児や成人ですと症状がハッキリしない場合が多いので、検査が行われないことが多いのです。そうすると、「いつまでも咳が止まらない」と訴えて受診される回復期に1回だけの検査になることが多く、仮に回復期で抗体価が上がっていても、急性期と比べてどの程度上がっているのか判断できません。つまり、1回だけの検査では診断が難しいのです。ただし、回復期1回だけの検査でも、非常に高値であれば百日咳と診断できる場合もあります。
ですから現実的には、「発作性痙攣性咳嗽」が診られれば百日咳を疑います。しかし、診られない時は、ハッキリした原因なしに2週間以上も続く咳、嘔吐を伴う咳、夜間に増強する咳、真っ赤になって咳き込む咳、痰が少なく乾いた咳、周囲に百日咳に罹った人がいる場合に百日咳を疑って検査します。
治療には、マクロライド系抗生物質が有効で、内服期間は2週間位です。「発作性痙攣性咳嗽」はすぐには治まりませんが、除菌効果(百日咳菌を体外に排出する効果)は期待できます。マクロライド系の抗生物質が無効な場合には、ニューキノロン系の抗菌薬やテトラサイクリン系の抗生物質が有効とされています。一般的な咳止めはまず効きません。強い咳止め(リン酸コデインなど)の中には、呼吸抑制作用がある薬品もあり、乳幼児に使用すると呼吸停止することがありますので、使用すべきではありません。
肺結核
肺結核は、結核菌という細菌が感染しておこる病気です。皆さんの結核に対するイメージは、「不治の病」、「恐ろしい伝染病」でしょうか?あるいは「一昔前の病気」でしょうか?
かつて、日本でも多くの老若男女が結核により尊い命を奪われました。結核は1950年以前の日本人の死因のトップで、当時の患者数は年間60万人以上、死亡者数も年間10万人以上という、まさに「国民病」、「亡国病」ともいわれていました。その後、有効な治療薬が開発され、ほとんどの場合「薬で治る病気」になり、さらに、早期発見・隔離、健診などの総合的な結核対策が効果を上げ、患者数は激減しました。現在の新規発病者数は60年前の約30分の1となり、一般の医療従事者の間ではまれな病気になりました。それでも、欧米の先進諸国と比べると患者数は3~5倍も高いのが現状です。現在、日本の結核患者の約半数が高齢者ですが、都市部では20~30歳代の若い世代の発病が目立ち、都市文化を象徴するインターネットカフェ、ゲームセンター、カラオケ、サウナなどといった不特定多数が集まる場所での感染事例は絶えることがありません。
結核菌は、普通の細菌のように手の指や土の中、水回りなどにいるものではありません。通常は、感染したヒトの体内でのみ増殖し、発病したヒトの咳の中の菌が空気中を漂い、それを大量に吸い込んだ人にのみ伝染する病気です。
肺結核の代表的な症状は、咳、痰、血痰、胸痛などの呼吸器症状と、発熱、冷汗、全身倦怠感などの全身症状です。結核は、一般的な肺炎やインフルエンザなどの呼吸器感染症とは異なり、ゆっくりと進行し、初期の症状が軽いため、自分ではなかなか気づかず、残念ながら診断時にはかなり進行していることがあります。
同時に、接触した大勢の人に病気をうつしているかもしれません。そうならないためにも、早く医療機関を受診すれば、軽症で完治させることができますし、大切な家族や友人を感染させることも防ぐことができます。2週間以上続く咳は結核を疑うサインです。あまり気にならなくても、咳が続く場合は必ず医療機関を受診してください。
検査としては、喀痰中の結核菌の有無をみる喀痰塗抹・培養検査が一般的です。またQFT(クォンティフェロン)検査は、BCG接種を行っていても施行可能であり、結核菌に特異的に反応することが特徴的です。
治療は抗結核薬の内服で、最短でも6ヶ月間飲みます(最初の2ヶ月は4種類、その後の4ヶ月は2種類)。飲み忘れると、薬の効かない耐性結核となってしまうので、きちんと内服しましょう。治療終了後 2年間は再発しないか検査を定期的に受けていただきます。
肺炎
肺炎とは、何らかの病原性微生物が肺に侵入したことで起きる急性の炎症です。肺炎は、大きく市中肺炎と院内肺炎とに分けられます。前者は医療施設に入院していない方が罹る肺炎で、後者は文字どおり、何らかの医療施設の中で生活している人に起きる肺炎をいいます。
クリニックを訪れる多くの方の肺炎は「市中肺炎」に分類されます。
ここでは市中肺炎について述べてみます。肺炎は、環境中に存在する病原微生物が吸入されて気管支や肺胞実質に到達して増殖することと、それに対して私たちの身体が免疫応答を働かせてこれを排除しようとして炎症を起こすことによって発症します。市中肺炎の原因となる病原菌では、肺炎球菌の頻度が最も高く、その他にインフルエンザ桿菌、モラキセラ・カタラリスなどの細菌も肺炎を引き起こします。
一方で、マイコプラズマ、クラミジアなどの、厳密には細菌に分類されない病原体により肺炎が起きることがあり、こうした場合の肺炎を「非定形肺炎」と呼んでいます。さらに、頻度は少ないながらもウイルスにより肺炎が起きることもあります。
これらの原因の中で、肺炎球菌、レジオネラ、ウイルスは、時に非常に重症の肺炎を引き起こすことが知られています。さらに最近では、HIV感染の初発症状としてニューモシスチス・イロベッチによる肺炎が起きることがあり、しばしば重症になります。
年齢・基礎疾患の有無・咳の強さ・胸部所見の程度をもとに、細菌性の肺炎なのか、それ以外の肺炎(非定形肺炎)かを大きく推定・鑑別し、それぞれに見合った抗生物質を投与します。血液データや胸部レントゲン写真も病気の進展度の指標にします。痰の培養検査で原因菌が特定できた場合には、その菌に最も有効と考えられる抗生物質に変更することもあります。年齢や血圧、血液中の酸素分圧などを組み合わせてどれくらい重症であるかを判定し、治療方針を決定します。高齢者の肺炎では自覚症状や発熱などの所見に乏しいことがあり、呼吸や脈拍が早くなっていないか、脱水がないか、意識がしっかりしているかなどに注意をする必要があります。
肺炎の症状・診断
典型的には、発熱や咳、膿性の痰が出現し、レントゲン写真で肺に異常な影が出現した場合に肺炎を疑います。ただし、クラミジアによる肺炎では、発熱や胸部の聴診所見に乏しく、咳だけが持続することもあります。
一方、レジオネラ肺炎などのように、腹痛や下痢、筋肉痛、倦怠感の後に高熱を伴って重症化する場合もあります。一般的に、非定形肺炎では、肺炎球菌などの細菌による「定型肺炎」に比べて、年齢が若い、基礎疾患が無いか軽い、痰が少ない、咳が強い、などの特徴を備えていることが多く、これらのことを参考にして両者を大まかに鑑別します。
一方で、高齢の方が肺炎を起こした場合、時に自覚症状や咳・発熱などの所見に乏しいことがあります。こうした場合には、呼吸や脈拍が早くなっていないか、食欲不振や脱水がないか、意識がしっかりしているかなどに注意をし、肺炎の存在をまず疑うことが大切です。
原因菌を決定するためには、喀痰をグラム染色したり、あるいは培養して、病原性のある細菌が検出された場合、臨床症状と照らし合わせて原因菌とします。
一方、口腔内には病原性の無い常在菌も住んでいるので、これらの菌が痰から検出されても、病的な意義はないと考えます。肺炎球菌やレジオネラは、肺から菌が血液の中に入って全身を巡ることが多いので、尿の中の抗原価を測定することが診断を確定するためにしばしば有用です。
肺炎の治療
臨床的には、患者さんの背景や症状、重症度に応じて細菌性肺炎か非定形肺炎かを類推し、それぞれに適切な抗菌薬(抗生物質)を投与します。ただし、原因菌は必ずしも一種類と決まっているわけではありません。
例えば、非定形肺炎を起こすクラミジアは、細菌性肺炎との混合感染を高率で起こすことが知られています。ウイルスによる肺炎の場合には、原則として抗菌薬(抗生物質)は無効なので、対症療法が主体となります。
しかし、臨床的にはウイルス性肺炎とそれ以外の病原菌による肺炎を区別することはしばしば困難なので(CT撮影をすれば区別できることもあります)、症状があってレントゲンで影がある場合には、ウイルス以外の病原体による肺炎の可能性を念頭において抗菌薬を投与します。逆に、咳だけで膿性の痰がなく、レントゲンでも異常な影が見つからない場合、ウイルス性の気管支炎の可能性が高いので、これだけでは原則として抗生物質は投与しません。
ただし、いわゆるハイリスクグループの患者さん(免疫抑制状態、著しい高齢、重症の肺の病気がすでにある人など)では、状況によってはウイルス感染に引き続いて二次性に細菌性肺炎を起こす可能性を疑い、抗生物質を投与することはあります。適応を見極めずに抗生物質を濫用するのがなぜ良くないかというと、そのことでその薬が効かない耐性菌を作りだす可能性が高まるからと考えられています。
治療を開始した場合、通常は数日から1週間後に診察し、身体所見と様々な検査所見を組み合わせて治療の効果を判定します。効果が不十分あるいは無効の時には、再度評価して抗生剤を変更あるいは追加して治療いたします。
肺癌(がん)
肺がんの標準治療における5年相対生存率(※注)は男性で25%、女性で41%と、あらゆるがんの中でも最も治療の難しいがんとされています。
その理由には、肺がんは進行が早く転移をおこしやすいがんで、発見時には既に「リンパ節、脳、骨、肝臓、副腎」などに遠隔転移をおこしていることが多いことがあげられます。
したがって、早期発見が非常に重要です。
(※注)肺がんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体(正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団)で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。
肺がんの症状について
肺がんの一番多い症状は「咳」
- 咳(3人に1人程度)
- 血痰・胸痛・喀痰(10~15%)
- 自覚症状なし(20%前後)
その他 発熱、倦怠感、呼吸困難、嗄声、体重減少など
- 血痰…たんに血が混じること
- 喀痰…たんを吐くこと
- 嗄声…声のかすれ
肺がん特有のものは10人に1人程度なので、症状で気が付くのはなかなか難しいがんです。
※咳で、3人に1人、血痰、胸痛、喀痰が10~15%、症状がない人が20%前後、その他、発熱、倦怠感、呼吸困難、嗄声、体重減少などありますが、肺癌特有なのは血痰で10人に1人程度なので、症状で気が付くのはなかなか難しい癌です。
肺がんの検診について
肺がんの検診は胸部X線が基本ですが、喫煙歴がある場合40歳から、喫煙歴がない場合50歳から胸部CT検査を毎年受けることをお薦めしています。
胸部CT検査による被ばく量は1回に7から10mSv(ミリシーベルト)です。
1回に100mSv以下の被曝では健康被害が出る可能は考えにくいとされています。
肺がん検診は現在、X線検査からCT検査への移行期に入っています(CTによる検診が必要と海外では考えられています)。
肺がんの診断について
肺がん検診は、胸部X線撮影が基本ですが、発見率が0.04%(1万人に4人)というかなりかなり低い発見率です。
つまり、肺癌を早期に発見するためには、定期的な胸部CT検査が必要です。
過敏性肺臓炎
アレルギー反応が原因で生じる肺炎の一つに「過敏性肺臓炎」があります。
一般的な肺炎は細菌やウィルスなどの病原体が肺の奥にある小さな袋状の部分(肺胞、はいほう)に感染して引き起こされる炎症ですが、過敏性肺臓炎では、それ自体は本来病原性や毒性を持たないカビ(真菌)や動物性蛋白質などの有機物、あるいは化学物質などを繰り返し吸い込んでいるうちに肺が過剰反応を示すようになり(これを「感作」と呼びます)、その後に同じもの(抗原)を吸入すると肺胞にアレルギー性の炎症が生じます。
アレルギー反応はI型からV型に分類されますが、気管支喘息やアレルギー性鼻炎などがI型(即時型;吸入アレルゲンが体内に侵入すると早くて10分くらいで症状が発症する)に分類されるのとは異なり、過敏性肺炎はIII型(3~8時間後くらいに発症)とIV型(24~48時間後くらいに発症)アレルギーに分類されます。
過敏性肺臓炎の症状
抗原にさらされると強いアレルギー性炎症が生じ、発熱やせき、呼吸困難感、だるさなどの症状があらわれます。抗原の多くは患者さんの自宅や職場に潜んでいるため、その環境から離れると症状が軽快・消失し、再びその環境に戻ると悪化します。
過敏性肺臓炎の検査
胸部エックス線検査や胸部CTでは肺全体にすりガラスのような陰影がひろがっています。血液検査で特定の抗原に対する抗体の有無を調べます。入院していったんよくなったあとで、疑わしい環境(自宅や職場)に戻ってもらい同じような症状が再び出現するかどうか調べることもあります。
過敏性肺臓炎の治療
治療の基本は原因となっている抗原を避けることであり、自宅の改築や転職を余儀なくされる場合もあります。症状が強い場合は入院してステロイド薬による治療をおこなうこともあります。
日本でよくみられる過敏性肺臓炎
夏型過敏性肺臓炎
高温多湿になる夏季に発症しやすく、冬季にはみられません。風通しや日当たりが悪く湿気の多い古い家屋を好むトリコスポロンというカビが抗原です。秋田県や岩手県以北では稀です。
農夫肺
北海道や岩手県などの酪農家にみられ、干し草のなかの好熱性放線菌というカビが抗原です。
換気装置肺炎(空調肺、加湿器肺)
清掃を怠ったエアコン(空調)や加湿器に生じたカビ類を吸い込むことによって発症します。
鳥飼病
鳩やインコなどの鳥類を飼育しているひと、あるいはその周囲で暮らしているひとに発症します。抗原は鳥類の排泄物にふくまれる蛋白質といわれています。
職業性の過敏性肺臓炎
キノコ栽培業者がキノコの胞子を吸入して生じる過敏性肺炎やポリウレタンの原料であるイソシアネートを吸入して生じる過敏性肺炎などが知られています。
間質性肺炎
間質性肺炎は「肺炎」とついていますが、一般的に細菌やウイルスで生じる肺炎とは違い、肺が徐々に硬く縮んでいく病気です。別名「肺線維症」とも言われる所以です。原因はよくわからない特発性、膠原病(関節リウマチ等)、アレルギー、薬剤など様々です。
まず、間質性肺炎の症状としては慢性的な咳・息切れです。50歳以上の男性の方に多いのが特徴です。喫煙の影響とも言われております。
進行すれば肺活量や肺拡散能(酸素の取り込み能力)が普通の人の半分以下になるなど、ちょっとした動きでも息切れがひどくなります。最終的には酸素療法や人工呼吸器による治療が必要となってきます。
間質性肺炎の診断
胸部CT写真、X線写真、呼吸機能検査、必要に応じて気管支鏡が必要です。
間質性肺炎の治療
現在のところ必ず治る特効薬はありません。膠原病など原因がはっきりしている間質性肺炎については、原因となった病気の治療をすることで改善の余地はありますが、原因がわからない間質性肺炎については、進行を抑える程度の薬しかないのが現状です。進行が早いものであれば、2年半程度で酸素療法や人工呼吸器が必要な場合もあります。
従って、間質性肺炎の原因が何かをつきとめることが重要となってきます。早期診断・早期治療により、早い段階で進行を抑えることが大切です。
また間質性肺炎の方で、気道感染を契機に、急激に呼吸困難が増悪することがあります。
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。
塵肺(じん肺)
鉱物、金属、研磨材、炭素原料、アーク溶接のヒューム等の粉じんを吸入すると、比較的粒子の大きなものは鼻孔や気管支等に付着して「たん」となって体外に排出されますが、微細な粉じんは肺の奥深くの肺胞(肺の奥にある小さな袋状の部分)にまで入り込み、そこに沈着します。
これらの粉じんを吸い続けると、肺内では線維増殖が起こり、肺が固くなって呼吸が困難になります。これがじん肺です。
塵肺の症状・所見
粉じんを吸い始めてから発症まで、早くても数年はかかります。最初は自覚症状がありませんが、痰や咳が出始めるころにはかなり病気が進行し、続いて息切れや呼吸困難となります。
また、肺全体に小さな粒状の影が認められますが、進行すると結節影を形成し肺癌との区別が困難なケースも見受けられるようになります。またじん肺は、肺結核の発症のリスクが非常に強いため、痰などが出る場合は肺結核の診断あるいは除外診断が必要になってきます。
塵肺の治療
ベリリウムによるものはステロイド剤が有効です。その他は根本的な治療方法にはなりません。気管支拡張剤(ホクナリンテープ、セキナリンテープ)を張り、肺内の分泌物を排出する粘液溶解剤などで気道を清潔保ち呼吸しやすくすることが治療の中心となります。
粉塵を吸う仕事歴のある方は、じん肺の治療等の経験豊富な当院に一度相談してください。
